
葉隠(後編)
和田夏十の言葉
確かなもののない時代に、小さな確かなものを無理無体に造り上げ、それを確かなものであらせ続けるために死力を尽くすというのは、いじましい。
『和田夏十の本』「(『葉隠』上を読み終わった)」より
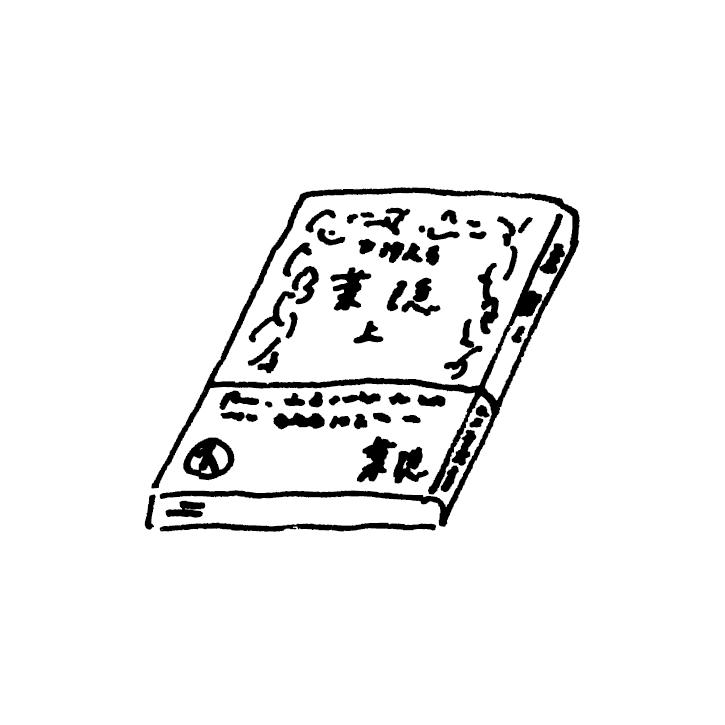
私の祖父は大正10年の生まれだ。そして祖父が生まれる前年の大正9年、西暦でいうと1920年に生まれたのが和田夏十だった。
『和田夏十の本』には、子ども時代の和田夏十が、「士族」の身分に執着していたことがわかるエッセイが収められている。
「私ひとりぢゃないと思うのですよ。私くらいの年頃の人々は、そういう風にして育った人も沢山いたんぢゃないかと思うのです。」
「私くらいの年頃の人々」には、私の祖父も含まれるだろう。私からするとはるか昔に思える武士の世も、和田夏十や、私の祖父の世代からすれば辛うじて手の届く範囲であることがわかる。
彼女はこう続ける。
「でもその痕跡もありませんよね、いまの日本人には。日常あたりを見廻してみて、その様なものが残っているんでしょうか生活の中に。」「いまやあとかたもなく消えてしまった、かつて存在した、自己規範、を不思議に思うのです。あれは何だったのか。あったものが消えるというのはどういうことなのか。」
「とにかくそんなわけで、私は武士道にこだわっています。大論文を書いてみたいなあと思っています。」
論文を書くには資料に当たらなければならない。この記述の2年後、和田夏十は『葉隠(上)』(山本常朝 著、和辻哲郎・古川哲史 校訂、岩波文庫)を読み終えた。
『葉隠』は江戸時代中期に書かれた書物で、「武士道の教典みたいなもんぢゃないかと考えてるわけね、だれでも。」と和田夏十は記している。しかし、その次に続く言葉は思いがけないものだった。
「読み終わった結果が、意外や意外、自分でもね。長い間こだわり続けた武士道から卒業してしまった、というのが実感なの。」
これは一体どういうことなのか。
「私が武士道を尊敬したのは、自己規制の見事さ、ひいては自立の精神であったらしいんだ。」「封建的であっても、封建制を突き破る立派さというか、人間洞察の確かさというか、そんなものだったのね。」
しかしその見立ては大きくはずれたようだった。
「なにしろ殿様というのが嫌になったのは、自分でもおどろいた。自分が殿様になったらと想定してみても嫌だった。どの殿様という訳でなく、殿様が存在する社会が嫌だと思った。」「殿にお供つかまつるというの、甘いのね。切腹して死んぢゃうわけだから、もの凄く辛(から)いことなんだけれど、それなのに、いやに甘い感じ。串ざしダンゴみたいにつらなってるって。お供される方も、する方も。とても独立独歩とは考えられない。そんなに堅く結びついていなければならないのだという甘さがいやらしい。」
「大論文を書いてみたいなあ」とまで思い慕った「武士道」を、「甘い」「いやらしい」という言葉を用いてひどくなじっている。また次に続く言葉は、2022年の今、ますます冴え渡って聞こえるように思う。
「武士道とは死ぬことと見付けたりと云うなら、もっと無常というものの上に足をふんばった生き方だって出来たのぢゃないか。確かなもののない時代に、小さな確かなものを無理無体に造り上げ、それを確かなものであらせ続けるために死力を尽くすというのは、いじましい。」
『和田夏十の本』では、「武士道」への強い情景を書き綴った記述に続いてこの文章が収録されている。そこには、この本の編集に携わった谷川俊太郎と、彼に編集を依頼した和田夏十の夫、市川崑の強い意志を感じる。
谷川俊太郎は、『和田夏十の本』のプロローグで次のように書いている。
「崑さんはシナリオ・ライターとしてよりも、時代に先がけて生きたひとりの女性として、夏十さんをこの本の中に残したいお気持ちのようだ。」
先述の和田夏十の文章の終わりは、こう締めくくられている。
「注釈なしに読んだのだから、全く分からないだらけだけれど、(略)分かっても分からなくても、自分で読んで、自分で感じるのがいいんぢゃないかって、そう思って、中、下、と読むつもり。また書くわね。」
書かれた日付は1982年7月22日。和田夏十が亡くなるおよそ半年前のことだった。

