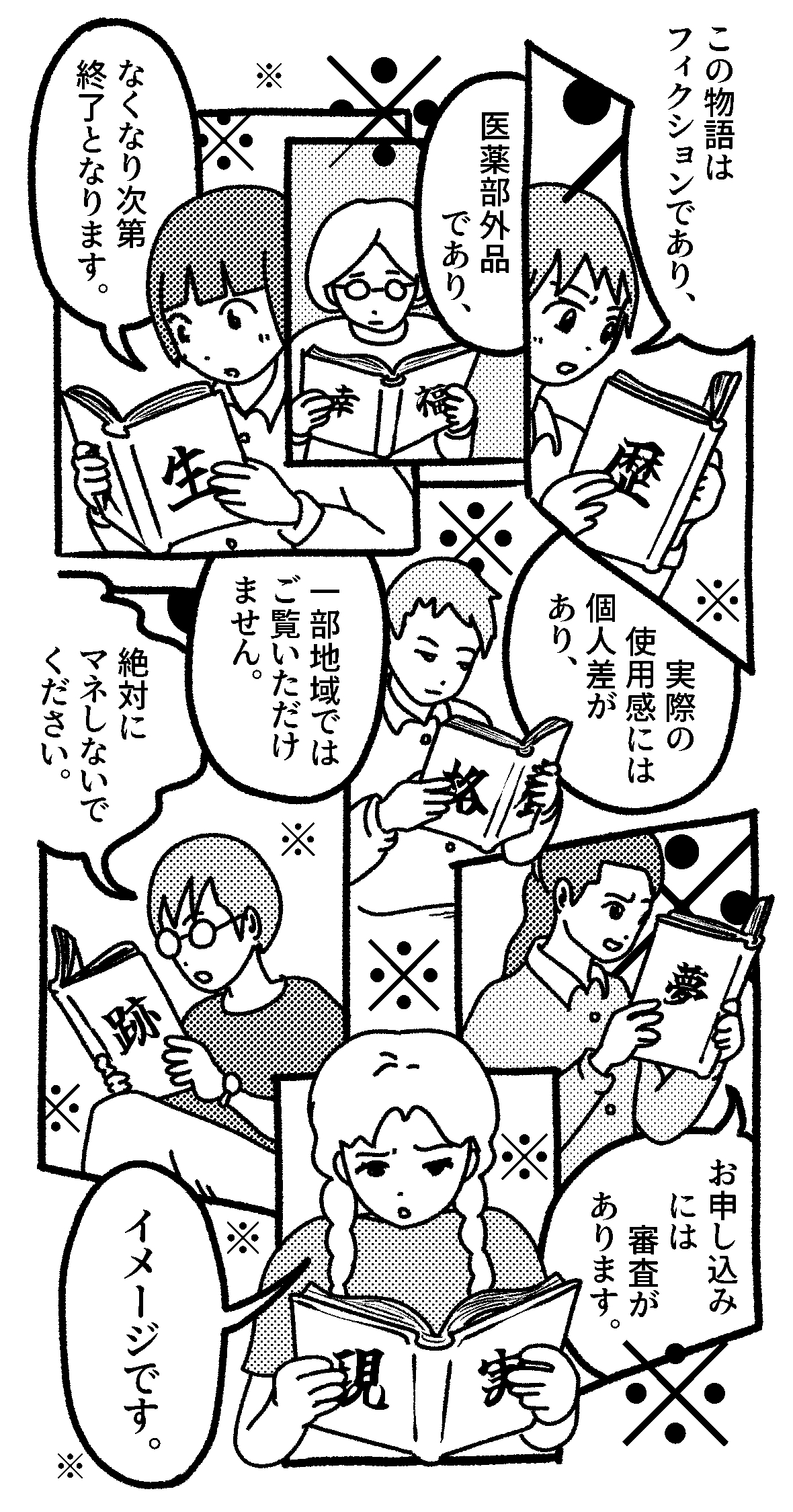※
なまえのこと
漫画ナマエミョウジ文フィクショナガシン
マルハラというのがあるそうである。「ハラ」というのはハラスメントの「ハラ」であるが、マルというのはなんだろうか。←これのことで、いや、もうちょっと下かな。↙︎これのことで、いや、こっちからいくか↘。これね。あ。逃げた。おい。こら。待てったら。待ちなさい↘。確実に仕留めるために両側から挟むか↘。↙︎カギカッコで捕まえた方が早いな「。」
。というのは句点のことであるが、LINEやチャットなどの文字メッセージ界隈では、どうやら、ハラスメントになる場合があるらしいのである。冷たい印象になってしまうのだそうである。
そうですね。
と、LINEなんかで上司などから送られてくると、冷たい印象だけでなく、威圧的だったり、怖いと思ったりされてしまうようなので、そう受け取られないためには、
そうですね
と句点をトルか、あるいは、
そうですね!
みたいにビックリマークをつけるといいそうである。若い世代とメッセージでやり取りする際には気をつけてください、みたいな、アドバイス込みの記事を私は何本か読んだことがある。
正直なところ、文章の最後に「。」をつけるかどうかなど、30年以内に南海トラフ地震発生80%時代を生きる我々にとっては些細なことであるはずだが、たった「。」があるだけで、読んだ人の気持ちが⤵︎してしまうというわけであり、物書きにとってみれば非常に興味深いことではある。そして、私は思うのであるが、つけない方がいいならつけなければいい。意味は変わらないのだから、と思うのである。
ところで、読点にせよ、句点にせよ、こんなに小さいのに、無視できないパワーを持っており、「ない」となると、多少なりとも混乱が起こってしまう。
そうですねねじの回転が止まらなくて
というように、文字と文字が衝突してしまうような感じがある。もちろん、あえてそうすることで文字の物質感を強調することはなくはないけれども、一般的には句点をここで打つのである。
そうですね。ねじの回転が止まらなくて
と、こうすると読みやすくなり、「。」はグッドジョブということになるのである。文末であれば「。」はなくても一向にかまわないのである。
ただ、
そうですね! ねじの回転が止まらなくて
と、「!」をつけてしまうと、「!」は、かなり存在感がある記号であるから「そうですね!」と「ねじの回転が止まらなくて」とのバランスが悪くなってしまうおそれがある。その場合は、
そうですね! ねじの回転が止まらなくて!
と、こちらにもビックリマークをつけてバランスをとるべきであるが、そうすると、弊害が出る。なぜなら、いささか元気よすぎる人になってしまうからである。こんな感じの人ならばいいが、人によっては自身の性格とのギャップを感じることもあるのではないだろうか。私は仕事のやり取りをメールでやることが多いのであるが、文章の最後に、
よろしくお願いします!
と、いつも書くのである。しかしながら、送信し終えた後で、「でも、俺、口頭で、こんなに元気よく、よろしくお願いします!なんて言ったことないな」と、メールの文章と、実際の自分の人格との乖離を感じるのである。だが、
よろしくお願いします。
になると、やはり、確かに寂しい。冷たい気がするのは、LINEでなくても、若者でなくても、なんかその感じはわかるのであり、それなら、
よろしくお願いします
がいいかというと「。」をつけ忘れていると思われたらイヤだな、という気もするのであって結局「よろしくお願いします!」となってしまうのである。では、実際の私が対面でよろしくお願いしますをどう発声するのかこの場を借りて実演してみると「よろしくお願いします……」という感じなのである。もう少し詳しく表現すると「よろしく……お願いします……」かもしれない。人当たりが悪いわけではないと思うが、実は私は常に100%全力投球的に内向的で、いちばんの話し相手は自分であるような男なのであり、だいたいいつもそんな感じである……。
さて、今、「……」と書いたが、この「…」に対して三点リーダーという名前が付いていることを私は物書きになってから初めて知った。また、これも物書きになってから知ったのであるが、「…」で1文字分であり、計6個が基本形であり、2文字分として「……」が使用されるのが一般的である。もしかすると義務教育のどこかで習っているのかもしれないが全く覚えていない。
どうやら「……」という記号は中毒性があるようで、文字メッセージ界隈では「三点リーダー症候群」と名付けられているらしい。確かに日常的に便利に使ってしまっているかもしれない。自覚症状はないのだが、この「……」は、発信者の主体性を希薄にし、責任を押し付けてくるニュアンスが読み手に感じられるようなのである。使用には気をつけるようにというお達しがある記号のようなのである……。
ともあれ、「。」とか「!」、「……」などが、無視しできぬなんらかの感情を喚起するというのは非常に興味深いことである。この「。」にしても「!」にしても「……」にしても、声に出して読むことができないものであり、そもそも「 」自体、音読しないはずものである。通常会話文の際に「 」は使われるわけだが、実際の会話のように朗読する際に、カギカッコフィクショナガさんの誕生日って誰か有名人いますか?カギカッコ閉じ、カギカッコあのさあ、俺さあ、タイムマシーン3号の山本浩司と同じ誕生日なんだよねカギカッコ閉じ、カギカッコへえそれってすごくいいですね!カギカッコ閉じ、とは言わないのである。
だが、小学生のある時期、カギカッコ、カギカッコ閉じ、をそのまま声に出して読んでいたのを私は覚えているのである。小学3年だったか、2年だったか忘れたが、それくらいの頃だったと思う。国語の授業の時、生徒が教科書を朗読させられるのであるが、会話の箇所になると、カギカッコと言って会話の中身を読み上げ、カギカッコ閉じ、と言って会話の箇所を読み終えたのである。ところで、カギカッコ自体は、小学1年ですでに習うようである。光村図書の小1の国語の教科書で、最初に生徒が出会う物語は岡信子の「はなのみち」というお話であり、
くまさんが、
ふくろを
みつけました。
「おや、なにかな。
いっぱい
はいって いる。」
と、袋を見つけてそれを友達のリスさんに見せに行く。袋には穴が空いていて、着いた時には中身はからっぽ、でも、クマさんが歩いた道に花が咲く、袋の中にはお花のタネが入ってたからね、という内容である。この引用箇所は読解のテスト問題として使われており、その第2問が、クマさんの独り言のカギカッコに対して、
(2)「 」の ところは、 だれが いった ことばですか。
という設問になっている(『小学1年こくご 教科書ぴったりトレーニング』新興出版社)。ルビが振られているわけでもなく、「 」という形だけですでに了解されていることが前提になっているようである。もっとも、これとは別の小学1年の教科書を解説した本によると、同様の箇所に対して、
※カギといいます。
と、「 」の読み方が注釈として付いていた。ただ、カギカッコではなく「カギ」だったのが印象的である。そういえば、声に出して読み上げられるといえば、カギカッコだけでなく、まるかっこの場合も同じであった。まるかっこというのは、それこそ声にならぬ内心の声のようなものであるが、やはり、声に出した。
男は眠り込んだかっこ確固たる信念で扉は開けたままにしたかっこ閉じ。
という感じである。ただ、「まるかっこ」とは呼ばず、単に「かっこ」だけだったと記憶しているのである(謎は深まるばかりである)。いずれにせよ、カギカッコはカギカッコというふうに読み上げていたわけであるが、もし、多和田葉子の『聖女伝説』(太田出版/1996,ちくま文庫/2016)が小学校の国語の教科書に載っていたら、自体はやや複雑になるかもしれない。
〈反省しているのか。〉
と尋ねられ、答えずにいると、
〈罪の意識はないのか。〉
と重ねて尋ねられ、わたしははっとしました。教会で聞く話の中でいつもぴんとこないのがこの罪という言い方だと気づいたのです。
〈その罪というのが、どういうものか分からないのです。〉
〈悪いことをしたと思わないのか。〉
〈人の迷惑になった時にゴメンネという感じは分かるんですけど、本当に心の底から悪いという気持ちが分からないんです。〉
〈授業中に関係のないことを大声で言ってみんなの邪魔をして、悪いと思わないのか。〉
〈でも、あれは精霊が言ったのであって、わたしが言ったのではありません。〉
主人公の少女と教師との、放課後の職員室での痛快な会話シーンのひとつなのであるが、珍しいことに会話がヤマカッコで表示してあり、私は読んだ時に〈ほう、カギカッコじゃなくてもいいんだな!〉と一人思わず快哉を叫んだほどである。小学生がヤマカッコ閉じ、とか言っているのを想像するとなかなか楽しいのであるが、さて、私は一体何が言いたいのかというと、短期間ではあったと思うが、小学生時代のカッコ音読現象は、あれは一体なんだったのだろう、ということなのである。
「!」
という、完全記号100%の場合、どう朗読すればいいのか。
「……」
も同様である。「よろしく……」のように文章の下にぶら下げるのではなく、「……」だけで独立しているのである。これは無言、沈黙を意味しているが、内容的には三点リーダーを使用せずに表現することは可能であり、「彼は沈黙した」と書けばいいだけである。
「おい。なんとか言え!」
彼は沈黙した。
ではなく、わざわざ、
「おい。いいかげん、なんとか言えよ!」
「……」
というようにセリフと同列の場所を「……」に与えているのは、視覚的な効果を書き手は期待しているわけである。しかしながら、国語の時間の朗読を指名された小学生は、ここに突き当たった時、かなり困惑するだろう。
「……」
となるのではないか。
ところで、先日のタイムマシーン3号の関太じゃない方の誕生日の未明、米国大統領は、イランに対して初めて空爆した。バンカーバスターなる強烈な大型貫通爆弾で地下深くに隠された核施設を3か所破壊したというのである。真夜中の鉄槌Midnight Hammer作戦と名付けられたようであるが、事態の深刻さと不釣り合いなほど滑稽な作戦名である。実は前から「作戦名について」という回を私はやりたいと思っているのであるが、それはさておき、この6月22日に米国大統領によってゴーサインが出された爆弾投下が決定打となり、翌日のイランによる報復攻撃の後、24日にはカタールの仲介のもと、イスラエルとイランの戦闘の停止を米国大統領が宣言した。13日にイスラエルがイランの核施設を攻撃して始まった戦争は駆け足で終結に向かっていると世界に印象付けたが、その日のうちにイスラエルは再び攻撃を開始し、それに対してイランが態度を硬直化させるなど、停戦が早速破られてしまうのではないか懸念されたのである。米国大統領はNATOの首脳会議に出発する直前に、マイクを向ける記者団に対してコメントしたが、停戦合意を破って攻撃するイスラエルに対して怒りを露わにしており、
「この2つの国は長く戦ってきた。※※※※※※※※※。自分でどうしたらいいか、わからなくなっているのだ」
と、怒鳴っていたのを私はテレビの昼のワイドショーで見た(25日)。テロップでそう翻訳が出たのであるが、※で表現されたのは放送禁止用語だったとナレーションが加えられた。ピー音は入ってなかったと思うが、口汚く罵ったのであろう。※は米印と呼ばれる記号であるが、米国を代表する大統領の放送禁止用語の発言を隠すにはちょうどいい記号かもしれない※。
※米国大統領は、先月先々月には、我が国に対して、コメの輸入を拡大すべきである等の要求をしてきたが、コメ不足という現実はこの数か月ずっと続いているのであり、近所のスーパーではカリフォルニア米が早速並んでもなお続いているのである。
さりげなく注釈を入れてみたのであるが、どうだろうか。※というものは、先に見たように、コクヨのケシポンみたいな、何か言葉を人の視界から隠す、伏せ字としての役割を果たす場合もあれば、今やってみたように、注釈のマークとして、文章の横に小さくなってくっつき、消し去るどころか詳しい解説の言葉へと導くという、全く正反対の役割を担う極めて両義的な記号として使われているといえそうである。
ところで米印といっても、米国と印度のことではない。ただ、報道などでは「米印首脳会談」などというように、割と目にすることはある。※は「米」という字に似ているために米印という名前がついており、実際にお米屋さんを示すマークとしても使用されていた。江戸時代からあったという話もあり、店先の看板などにここがお米屋さんであることがわかるように掲げられていたりするのである。※について、整理すると、こうなる。
1.伏せ字
2.注釈
3.米屋の印
多様な用途に感心せざるを得ないが、②の注釈というのは、さらに2種類の使われ方があるようであり、ひとつは、先ほど使ったような、文章に小さくなってくっついて詳細な解説へ誘導する注釈のあり方である※。
※このように文中に割り込む形で使用されるのは、しかし、実際は、※よりも、*が多いようである。番号が、*1、*2、*3というように番号が振れるからであろう。※でもいいのであるが※は日本語独自のものであり、英語圏の慣用がそのまま使われているのだろうと思われる。[1]、[2]、[3]のように数字だけで直接注釈に導く場合も多い。そのほか、デザイナーによって趣向を凝らした記号があてがわれる場合もあり、★1、★2、★3などがあるが、チカチカして本文に集中できない恐れもある。
もうひとつは、※だけが独立して注目を引くように使用される場合である。さっきの「はなのみち」のところに書いたように、
※カギといいます。
という、注目してほしいところの上に載せるという注釈の形である。パンフレットや、広告、案内状などで目にすることが多いだろう。
※車でのお越しはご遠慮ください。公共交通機関をご利用ください。
※駐車場はありません。
※平服でおこしください。
※本連載は今回で終わりです。
というような使い方である。その場合、※は、「おーい、こっち見てよ!」と主張しているわけである。よく見ると、なんだか小学生が元気よく両手をあげて、その両手の下からさらに2人の同級生が、また、股下からもう1人が、こっちに向かって「おーい!」とこっちに向かって呼びかけているように見えなくもないのである※。
※ところで本当に今回で連載はひとまず終わりである。終わりというのはいささか言い過ぎかもしれない。なぜならまた再開するからである。それならお休みというのがいいのかもしれないが、お休みしている数ヶ月の間、何をしているのかというと単行本化の作業をやっているはずなのである。この連載は来年1月あたりに、漫画も文章も書き下ろしを加えて、誠光社から本になる予定なのである。デザインは仲村健太郎氏であり、どうやら彼の最高傑作のデザインになるようである。また、漫画は新作のほかに、すでにこの連載で発表されたものに加筆修正するとナマエさんが言っていたのを聞いた記憶がある。最高傑作になってしまわざるを得ないようである。誠光社の堀部篤史氏においては、今まで彼が書いた自社の数々の帯のキャッチコピーの中で、最高傑作を書くことが運命づけられている。私はといえば、書き下ろしのほかにたぶん全14回のこれらの文章に注釈をつけると思うのである。いろんな「名前」がこの連載では出たのであるが、そういう名前や名前っぽい部分に注釈をつけてみたいと思っているのである。単行本を楽しみにしていてくださると嬉しいです。